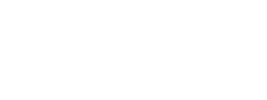信じたかったのかもしれない。
ローレこそが選ばれた者で、全てを背負う者だと。
サマルトリアは付属品でしかないと思い込むことで、自分自身の弱さを正当化したかったのだろう。
「…あ、れ?」
朝、何時ものように目覚めたはずなのに動かない体。
全身が重く、息が上手くできない。
昨夜は水の都ベラヌールに皆で泊まっていた。
その前後に何かあった記憶はない。
何がどうなってるのだろう。
ぼんやりと天井を見つめて考える。
何も思い浮かばない。
(これがハーゴンの呪い…)
一時期、呪いにより犬にされていたムーンから、ハーゴンは人を呪い殺すことができると聞いた。
この取り巻く瘴気は間違いなく魔のモノ。
唐突なこの現象は間違いなくそれの一種だろう。
まさか、遠距離でもそんなことができる手段を手に入れているとは、さすがに思わなかった。
術者が紛れ込んでいたかとも考えたが、それに気づかないのは流石に落ち度である。
知らぬハーゴンの笑い声が聞こえた気がした。
なぜそこまでロトの血を引く者達を恨んでいるのだろう。
水の都ベラヌール。
他の町より華やかで中央の教会と思わしき建物は厳重に警備されている。
嘗て精霊ルビスの巡礼地の一つとされていた。
今は逆にどこがどうと言うわけではないが、華やかな町並みだと言うのに空気が重く濁っている。
そんな印象を受けた。
ローレとムーンは町人の情報に目がいっているようで、その不気味さを感じていないようだった。
確かに稲妻の剣や水の羽衣は魅力的だよね。
「サマル!? どうしたんだ?」
現実逃避とも言えるどうでもいい事に思考を巡らせているとローレの声が響く。
視線をやれば、薄ぼんやりの視界に青いものが見える。
耳だけは正常に聴こえているようで安心した。
「か、体が動かない…。どうやらハーゴンが僕に呪いを掛けているらしい」
「どう言うことだ?」
ローレにとっては唐突なことだろうから、困惑するのもわかる。
サマル自身も確信があってそう言っているわけではない。
ムーンとの状況が違うし、今まで共にいた皆には、なんともないのが引っかかる。
「しかし、やられたのが僕一人で良かった……。多分、僕はもうダメだ。さぁ、僕に構わず行ってくれっ! ううっ…」
「サマル!?」
強く肩を掴まれた時、激痛が走る。
言葉にならない叫びが口から飛び出す。
「ローレ! ここは抑えて状況を確認しましょう」
ムーンの言葉を微かに聞きながら意識を手放した。
「ハーゴンは遠くからでも人を呪い殺すことができると言うが…」
ベッド上から声が聞こえる。
「どうにかできないのか?」
誰かを連れてきたのだろう。
声から推測するに高齢の男である。
杖の音が床から聞こえるので、神父ではないだろう。
ただの知識の豊富な男かもしれない。
「ここはハーゴンのいるロンダルキアの地ではない。呪いのチカラも弱いはずじゃ」
ハーゴンは今、直接手を下さず、多くの魔物を携えそれを駒のように動かしている。
本人はロンダルキアで何をしているのだろう。
「もしかしたら、世界樹の葉でお仲間を助けることが、できるかもしれんぞ」
「世界樹の葉だな! サマル待ってるんだぞ」
既に言葉を紡ぐことすら困難なサマルを励まし、そして、その勢いのまま出て行くローレの足音だけを聞いた。
ムーンの声は聞こえなかった。
彼女がハーゴンに一番執着していたから、見捨てられても致し方ないかもしれない。
世界樹の葉か。
どこにあるか、わからないそれが見つかる可能性は低い。
(僕はどこまで出来損ないなのだろう)
纏まらない思考で思う。
あの二人ならこの先の道中も二人だけで何とかなってしまうのではないだろうか。
襲い来る恐怖が胸を締め付ける。
時折、自分は中途半端だなと思う場面がある。
ローレのように重い鎧でも何でも装備できないし、剣も細身を主として扱っている。
軽い剣だろうが重い剣だろうが、最悪杖ですら武器として扱ってしまうローレ。
ムーンも杖以外まともに扱えないが、魔力が多く魔法の扱いに長けている。
勿論、自分とムーンでは被っているものもあるが、それぞれ違う呪文を覚えているので役割が違うと言えるだろう。
しかし、低燃費で集団攻撃ができる呪文バギの強さを目の当たりにすると、何とも言えない気持ちになったのは記憶に新しい。
最近覚えたベギラマの呪文。
自身の最大の攻撃魔法である。
それで難を乗り越えれた時はやっと皆の役に立てられたと喜んだものだ。
しかし、それも魔力消費がキツイのであまり多用できないのがネックだ。
そんな中で一番辛かったのは、僕がロトの剣が装備できなかったことだ。
それはまるで勇者の魂に拒絶されたような気持ちになった。
ローレが目を覚ますまでずっと握り締めていたその剣は重く、魔法や筋力の差異だけではない気がする。
そう思えたのはローレのこの一言だ。
『よくわからないけど、ここが好きなんだと思うぞ』
竜王の城内部、ロトの剣を見つけたその空間でのことだ。
剣の意思を感じているのかはっきりと答えた。
サマルには何も感じなくて、軽やかに振るい何でもないように言うその一言。
ムーンと一緒に絶句した。
ロトの魂を引き継いでいるようなそんな印象を受けた。
だからこそ、自分が落ちこぼれじゃなく、ローレだけが選ばれた者で、残り二人は付属品だと思うことで心を守ったのだ。
「付属品どころか役立たずじゃないか」
サマルトリアができた経緯もそうだ。
ムーンブルクのような巨大な魔法の王国でもなく、ローレシアのように勇者が建国した由緒ある国でもない。
勇者の子どもが皆一人一人国を治めるように溢れた三人目のための国と言っても過言ではない。
それなりに木々が豊かで平和な国であり、隣国が全て友好国だ。
武器訓練は対魔物ぐらいだったろう。
しかも、ほぼ無害なこの地域のモンスター相手では闘志も下がる。
他国に比べて、どっち付かずで魔法と剣を訓練していた。
『勇者は両方できていたので、魔力のないローレシアの王子は半端ものだ』と言う噂も聞いたこともある。
しかし、本人に会えばそこを気にしているのがバカらしくなる程、彼は優秀であった。
対大神官ハーゴンを打つべき存在。
ローレとどちらが勇者かと言えば、口を揃えて皆ローレと言うだろう。
「僕は勇者どころか仲間ですら居られないなんて…」
動かない身体。
両手で顔を覆うことも許されない。
悔し涙すら許されないなんて…闇に堕ちて行く思考。
人はこうやって絶望して逝くのか。
「サマル」
それを解いたのはムーンの声である。
「大丈夫。あなたも私も歴とした勇者よ。竜王を倒した勇者の子孫だもの」
ゆっくりと撫でられる。
動かない体であることがもどかしいぐらい優しいものであった。
「だからハーゴンは私達を殺せない。呪うしかできなかったのよ」
ムーンは犬に、サマルは動けぬ身体に、これがハーゴンの呪い。
弱い心を支配する呪い。
「あなたが私を助けてくれたように私も助けるわ」
ムーンが祈ると世界樹の葉が光り輝く、重くのしかかっていた身体。
根元を切断されていた神経が全て繋がって、一気に電流が流れ出して行くようにビリビリと感じた。
持ち上がる手。
先程の苦痛が嘘にように軽くなる。
体を起こすとムーンが綺麗に笑っていた。
「サマルがいないと大変だったぞ。サマルはやっぱり凄いんだな!」
ローレが回復したサマルに向かって疲れたぞと笑顔で溜息をつく。
「そうね。ローレの暴走をフォローするのは一人じゃ無理だわ」
そうじゃないでしょと言いたげなムーンだが、ローレの言葉に同意する部分があったのだろう、溜息吐き混じりにそう言う。
「……二人共。ありがとー」
先程のムーンの言葉もそうだが、ローレの何気ない一言も落ち込んだ心には効果覿面だった。
三人で一つ、その言葉がこれほど嬉しいものだったとは思わなかった。
「ちょっとサマル!?」
「サマルが元気だぞ!」
ベッドから跳ね起き、二人に飛びついたのはご愛嬌だ。