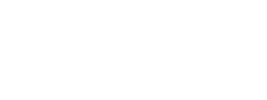ラダトーム城の死角にある城壁に囲まれた隙間を歩き、池の縁に地下へ降りる階段がある。
以前来たときと変わらず薄暗い地下に賢者がいた。
「なぜ太陽の石を守っておったかか?」
「はい。あのときすぐに追い出されたので、詳しく聞きたいと思ったのです」
詳しく聞くな、そう言われたような気がしたのだ。
だが、今は大丈夫ではないかと。
「無事、勇者になったな。ならば知っても良いか」
「やはり勇者とは選ばれた存在というより、成し遂げた存在なのですね」
確かめるように聞くと、目を閉じ、深く頷く。
「アレフよ…。そなたがこの地に、再び光をもたらすことをわしは信じておったぞ」
選ばれた多くの中の一人だったのだが、その中でも己のことを信じていたというのか。
「それはどういう……」
「わしに太陽の石を預けに来た勇者ロトの姿は、今でもはっきり覚えておる」
言葉を遮られたが、そんな事より発せられたその意味が分からず戸惑う。
「そなたには確かに勇者ロトの面影が…」
「待ってくれ、勇者ロトを知っているのか!」
この老人はロトが神器を託した賢者子孫じゃなくて、その人だというのか。
自己の混乱をよそに淡々と語る古の賢者。
「万里の理に背いた人の末路と言うべきかのう。皆、言葉を託し、朽ちて逝く」
謎かけのような答えのない問いのように、質問の答えがするりと逃げる。
言葉に窮すると話は終わりと老人は立ち上がる。
「さて…。長い間、太陽の石を見守りつづけてわしも、少しばかり疲れたわい。そろそろ 休ませてもらうことにしようかのう…」
ゆっくりと地下の寝床へと歩む。
その後ろ姿に、何も言えなかった。
何かを知っている。
だけどそれは口に出したくないものだと、そう言っているようだ。
ゆっくりと地上へと戻る。
「逆に謎が深まっただけだな」
一度振り返るも、この地下室の謎と同じく暗闇が見えるだけであった。
(しかし、あの賢者は幾つなんだ?)
もしかして、勇者ロトってそんなに前の存在じゃないのか。
数百年、いや、数千年前と言われている存在のはず。
普通の人間なら生きてはいない。
変な方向に想像が行き、ぞくっと身震いして城へと戻る。
城へ戻るとローラ姫が何時もよりラフな格好で、出迎えた。
「アレフ様、お話は聞けましたか?」
「少しだけですが」
頬を染めて、お役に立てて嬉しいですわと喜ぶ。
「お父様の許可を頂きましたの。ローラは何時でもいけます。直ぐに出発しますか?」
あー。やはりついて行くつもりなのですねっという言葉がでかかったが飲み込む。
己に拒否権はない。
「そうさせていただこうと思います」
そういうとローラは嬉しそうに微笑んだ。