勇者とは何か。
勇者とはどうあるべきか。
人々は口々に言う。
『世界を救う者』
『他の人が成し得なかった偉業を成し遂げる人物』
『最後の希望』
——…どれも正解だろう。
しかし、役目を果たしたその人はその後どうなったのだろうか?
「アレフ様? どうなさったのですか?」
ここはラダトームのお城。
この城の一角にある書庫で調べ物をしていたら声が掛かる。
書物から顔を上げると、この国の姫君が首を傾げて覗き込んでいた。
「船ができる間は暇なので、改めて調べようかと…」
狭義のアレフガルド——ラルス王が住まうラダトーム城の影響下にある領域——は全て巡った。
昔語りの町ガライ、温泉の村マイラ、湖の町リムルダールに、滅びた町ドムドーラ、そして、要塞都市メルキド。
その中で、喉の奥に小骨が刺さったような僅かな引っ掛かりを感じていた。
妙にスッキリとしないそれを解きほぐすために、最初はラダトームのお城のからと思ったのだ。
「何をですか?」
王の許可を得て見せてもらっている本を閉じ、タイトルが分かるように姫に見せた。
「伝説の勇者ロト。この人物のことを私はあまりにも知らな過ぎると思ったのです」
ロトの血を引きし者として祭られ、宿敵である竜王を意思のままに倒した。
死活の問題だったため、何も考えずに倒したが一体、この世の悪とは、そして光の玉はどう言う存在なのか、何も知らずに戦っていたのだと気付いた。
「『世界を救いし空から舞い降りた伝説の勇者。光を玉を用いて世界を平和へともたらした』と言われていますね」
子どもでも諳んずることができる有名な一節。
「そうどこの誰がなんのために、その後はどうなったのか。誰も知らないのです」
己が伝説の勇者を準えて、打ち果たした竜王はなぜ光の玉を盗んだのか。
なぜ伝説の勇者は再び蘇ることを知っていたのか。
だからこそ、知りたいと願うようになった。
「私は私である、それは確かです。ですが歴史はいずれ、私を消すでしょう」
「…消させません。あなたがいかに勇敢であったか、全て記録しましょう。私、ローラをドラゴンから救い、試練を乗り越え、竜王を倒し光の玉を取り戻した勇者は、ローラにとってただ一人。アレフ様、あなただけです!」
身を乗り出し、己の手を掴み、必死の訴える。
予想外の姫の強い言葉にタジタジになるも、どこかこそばゆさを感じる。
「分かりました。アレフ様が納得できる方法を探しましょう。ローラは何時もあなたの側におります」
一人納得し、握った手を強く握りしめ、決意を表明する。
「あのローラ姫?」
「少しお時間を頂けますでしょうか? 身支度を整えたく思いますわ」
ゆっくりと可愛らしい笑みなのに、この有無と言わせぬ迫力があるのは、なぜだろう。
あのときも、拒否権は無かった。
「………はい」
短く答えると満足したように手を離し、頬に手を当ててから。
「嬉しゅうございます。…ぽっ」
と、恥ずかしそうに身体をくねらす。
そして、毎度お馴染みっと言ったら失礼かもしれないが、愛の言葉をもらう。
(この様子だと、この旅にも付いて来る気だろうな)
手にしていた本を見つめて思案する。
始まりはここの王になることを断り、旅立つと宣言したあの日、代わりに褒美として欲しいものを聞かれたので、ラダトーム領外に出るための船をお願いしたのだ。
その船はお古ではなく新しく作るため暫くかかる。
もしかしたら、その船にローラ姫が同行するので、その時期を先延ばしにしようとする魂胆もあったのかもしれない。
その間、自分は何もできないので、引っ掛かりを覚えたことを解決しようと、動き出したその時である。
「参ったな」
いくら平和と言えども、完全にモンスターが消滅したわけではないので、道中は危険だ。
この説得で折れる姫ではないことは、十二分に実践済みである。
こちらが『はい』というまで諦めない強引さは見習いたいものである。
言うなれば、己の運命は贈り物(王女の愛)を受け取ったときに決まっていたのだ。
いや、助けることを選択した時点かもしれない。
「アレフ様。太陽の石を管理なさっていた賢者様にお話を聞いてみてはいかがでしょう?」
いいことを思いついたと手を合わせた彼女に、声を出さずに頷くだけに留める。
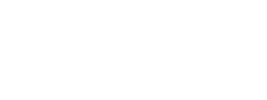
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます