ここはリリザの町。
聖なるナイフを買いに一旦、ローレシア大陸に戻った一行。
その夜。
ローレは既にベッドで大の字になって眠っている。
宿についたら直ぐに何もせず夢の中へと旅立った。
まるで、見知らぬ場所に旅行に来て、日中はしゃぎ過ぎた小さな子どものように…。
世界の平和が脅かされて、ロトの血を引くもの達がその討伐に向かう。
大それた使命を背負っているはずである。
そのことを微塵にも感じさせない豪快な眠りである。
「大丈夫ー? 疲れていない?」
コトリと呆然とローレを眺めていたムーンのすぐ横のテーブルに温かい飲み物、匂いからして紅茶であろう。
見知った銘柄ではないので詳細はわからない。
ゆっくりと置かれたそれに視線を移す。
「ええ」
サマルの方へ向き、一度、お礼と共に笑みを蓄える。
全く疲れていないといえば嘘になる。
確かに慣れない旅路ではあったが、出会うモンスターは全てローレが相手し、ムーンはただ後方でそれを見ているだけだったので楽なものである。
魔物に襲われる恐怖がまだ残っている。
それでも今はロトの血を引く者としての責務を果たしたい。
憎き相手がそれであるのだから、迷いはない。
「明日からの予定を立てたかったけど、ローレ寝ちゃったしねー。今日は僕らも早く寝よう」
ミルクの入った紅茶に口を付けながら、ムーンもサマルもローレの方を向く。
「不思議な方ね。彼もあなたも王族でしょうに」
ムーン自身も、既に王国として成り立っていないが、嘗てはムーンブルクの王女であった。
それぞれの国のトップの一族が一堂に集結していると言うのに、何の飾り気もない普通の宿屋に寝泊まりして、護衛も付けずに旅をしている。
冷静に考えれば可笑しなことだらけである。
「僕もローレに会うまでは緊張したなー」
勇者の使命として王族に成ろうとも『悪が現れれば討伐する』と言う掟のようなものがあり、運悪くこの時代にそれが起きてしまったと言えばそれまでである。
「あら、そうなの?」
のんびりしているようでちゃんと気を使ってくれているのがわかる。
チャラけた雰囲気にクスリと笑う。
「僕はちゃんと挨拶しなきゃとか、言い回しはこれで良いかとか、色々考えてたんだけど、全て吹き飛ばされたなー」
サマルは目を細めて、思い出す彼の対応。
最近のことのはずなのにすごく懐かしく感じる。
「確かに…そうね」
彼の第一声は何だったか、いきなり抱きしめられたときは、慌てたものである。
「身分を隠さなければいけないのは確かだし、今は王族と言うより、悪と戦うロト一族の末裔としての方が重要だから、僕は一旦忘れようかなーって思っている」
全てが抜けるわけではないだろう。
生まれてこの方、王族として育てられて来たのだから、身に染み付いたものは無理だろう。
だが、敢えてそのように振舞っていた部分まで、窮屈に装う必要はない。
「そうね」
今後のことを考えると、何から手をつけたら良いのかわからない程、問題が山積みである。
その部分を今は敢えて考えずに、王族ではなく、ロト一族として最大の敵である大神官ハーゴンを倒す。
精霊ルビスの教えに反しモンスターを凶暴化させ、国を世界を滅ぼそうとする邪神を崇める凶悪な人物。
余りにも少ない情報では考えようがない。
「ローレはそのことについても、ちゃんと考えているのか、わからないけどね」
彼には先見の計画性はない。
純粋に知らぬ場所に行けるワクワク感、わからないものへの好奇心が一番に来ているように感じる。
その分、あれやこれやと考えてしまって、身動きが取れなくなる前に吹き飛ばしてくれるのだが…。
「あら? それでも彼は前に進んでくれているわ」
最終目標は知っている。
そこまでの過程が今はまだ何もわかっていない。
だが、それで焦る必要はない。
目の前にあることから地道にクリアして行けば、自ずと道が拓けるだろう。
そんな勇気を貰っている気がする。
自然とサマルをムーンを信用してくれて、押し潰されそうな重責を取り払ってくれている。
その純粋さがとても嬉しい。
「不思議だよね」
「本当に」
もう一度、二人はローレを見てクスクスと笑い合う。
良い人達に出会えた。
それがわかる今は、それを大切にしようと思う。
できることをやる。
それが一番大切だと思う。
「さて、僕らも寝ようか」
「そうね」
食器を片付けそれぞれ立ち上がる。
「おやすみー」
「おやすみなさい」
乾いた心に水を一杯入れたようなそんな温かな気持ちで、それぞれ床に着く。
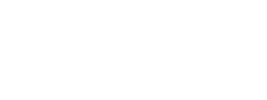
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます