冷たい風が頬を撫でる。
「ムーン! しっかりして、我を保ってお願いだから!!」
異様なサマルの叫び声。
ここまで声を荒げる姿を今まで一度も見たことない。
相当な緊張感が垣間見える。
ここで完全に意識を取り戻したローレは急いで起き上がり、あたりの状況を見る。
ここは世界樹のある島。
最後の記憶から一度死んで棺桶の状態でここまで来たことを理解する。
「ムーン?」
そんなことは何度もあったし、すっかり慣れた感覚になりつつあったが、ふとそれだけにしては様子が可笑しい。
「いや、いや、やだ。ダメ、また、また…私、所為でまた…いや」
どこを見ているのか、わからない定まらない視点。
何かを呟いているが、それは言葉の意味を成していない。
「ムーン! お願いだから僕を見て!」
サマルの声も届いていないようで彼の声にも悲壮感が出てくる。
「ムーンごめん」
サマルの横から手刀をムーンの首筋に落とす。
昔、爺が言っていた。
『パニックになっている人は一度落ち着かせる必要がある』と、眠らすことで心の整理ができるらしい。
「ローレ!?」
「何があったんだ?」
サマルと共に崩れ落ちたムーンを抱き抱え、サマルへと質問する。
ここにはまだ強めのモンスターがいる。
長居は危険だ。
「僕も全部はわからないけれど…」
意識を失ったムーンを気遣いながらサマルは憶測を交えながら城へ戻るまでの道中に今までの出来事を教えてくれた。
『ローレ!』
一匹を相打ちになるように倒した後、崩れ落ちるローレ。
飛ばした回復魔法が空を切る。
気付くのが遅れた。
しかし悔いている時間はない。
まだ二匹のキラータイガーが残っている。
一時退却するしかない、だがこのまま背を向けて逃げれるとは限らない。
ローレがかなり削ってくれていたのは確かだ。
『倒しきる』
この判断が不味かった。
攻撃体制のまま切り裂かれる体。
雷の杖を振り上げるムーンが眼を見張るのが見える。
次に標的にされたのはサマル自身だったのだ。
「その後、回復しようと思ったんだけどね」
間に合わなかった。
サマルは自分を嘲笑するかのように眉を下げて笑う。
「ムーンを独りにしてしまったんだ」
そこまで言われて気付く。
あの灼熱の中ムーンは生き残ってしまった。
全滅したのならローレシアで父の小言を聞きつつ蘇っていただろう。
その後は主のお守りを持っているローレが蘇生しに回り右往左往する筈だっただろう。
運良くと言うべきか悪くと言うべきか、ムーンだけが生き残ってしまった。
「初めてだったね。僕もローレも両方が棺桶に入っちゃったのが」
リレミトの呪文はムーンも覚えていたそうで、脱出には問題なかったと推測できる。
しかし、自分達が蘇ったのは教会ではなく世界樹の木の元。
「そうだったのか」
世界樹の葉を所持していたのはローレだったし、サマルがルーラを使えるようになってから、キメラの翼は持っていなかった。
なぜか遠いこの地までひたすら船を走らせたと言うのだろうか。
「僕達はあまりにも普通に振舞っていたから、彼女の心の闇に気付けなかった」
サマルは目を伏せて悔しそうに呟く。
世界樹がムーンの願いを受け我々を蘇らせてくれたのではないか。
「僕が目覚めたとき、彼女は既にあの状態だったんだ」
ムーンの視点は定まっておらず、壊れたレコードのように同じことを繰り返すのみ。
ムーンの心の打撃であるムーンブルクの滅亡と今回の騒動が偶然同じ状況に陥ったのだろうか。
「でもおれは死んでないぞ?」
便宜上『しに』という言葉を用いているが、実質、死亡しているわけではない。
蘇生できる死と言うべきか、ロトの御守りの加護がある限り御魂は天へと導かれることはない。
「その辺りは言葉の真の意味と使われ方の差異と言うか。うーん。それよりも、ムーンにとってはこの御守りも万全ではないと言う恐怖かなー」
説明しにくいとサマルは唸る。
既に少し混乱しているローレにとってこの先の説明を理解できるか不明である。
「先代の勇者、即ち竜殺しの勇者が残した話では『この御守りは悪に染まりし者、生への執着が亡き者、他何らかの原因により、加護が働かず御魂を呼び戻すことができないことあり』ってあって、いろんな事例がある。この御守りが一般に支給されていない理由が生産性以外にも不確定要素が多々あるからだと言われているんだ」
悲しそうに笑うサマルの説明を聞きつつ、この御守りの凄さと危うさだけは、難しい考えを拒絶する頭でもわかった。
「完全? じゃない御守りが原因で? おれらがこのまま死ぬ? かもしれないと言う怖さがムーンを可笑しくした? と言うことか?」
自分で言っておきながら一つ一つに疑問符が付くほど飲み込めていないのがわかる。
サマルの言葉を鸚鵡返ししているに過ぎない。
「あくまで僕の憶測だけどね」
肯定しつつその言葉で締め括ったサマル。
風に揺れるムーンの髪を撫でる。
抱きかかえたムーンは微動だにせず昏々と眠っていた。
「これぐらいでいいか?」
眠っているムーンをサマルに任せ、ラダトームの町の道具屋で必要なものを購入。
と言っても鍵類や必要装備を持っているとほぼ他に持てないのでサマル達の魔力が切れてしまった時の最終手段となるわけだが。
「力の盾もう一個いるか?」
力の盾は道具として使うとベホイミぐらいの回復量になる。
力の盾の中央に嵌められている石が魔力を持っていてどうのこうのと一応説明してもらっていたが、理解できていない。
わかったのは雷の杖同様、ローレでも掲げるだけで効果を発揮すると言う素晴らしいものであるということだ。
『そんなことする暇があったら攻撃しなさい』
そう言われていたのを思い出したので保留にする。
「結局買わずじまいだったんだぞ」
その足で武器屋に立ち寄り、大金槌を見つける。
当時は欲しいと思っていたが今では物足りない武器に成り下がってしまっている。
あの時もロトの剣が手に入ったので存在を忘れていた。
寄り道ばかりしていたら怒られるなと、眺めてるだけでも楽しい武器屋を後にしようと思ったが、入口の奥に登り階段を見つけた。
立ち入り禁止にしていないので興味本位で上へと足を向ける。
「こんなところまで来るとはしかたのないやつだな。わしはただの武器屋の隠居じゃよ。かっかっかっ!」
金のカギで開く扉の奥にラダトームの王様と思わしき人物がいた。
誤魔化すように笑うが、着飾っている装飾品が庶民ではありえないものである。
流石に嘘であることはわかる。
「………」
「軽蔑したか? 勇者の血を受け継ぎしローレシアの王子よ」
不自然な笑みを消しローレの心を読むが如く哀愁を含んだ眼差しで見る。
「精霊ルビスに愛されし血を受け継ぐものよ。わしはそなたらが羨ましい」
何をもってそう言うのだろう。
スッと指し示すは懐の御守りである。
またこれかと眉を顰めてしまう。
「ムーンブルク王もさぞかし渇望しただろう。しかし、生き残ったのは王ではなく王女じゃ」
選ばれなかった者の末路それはただの死。
蘇ることも無く地に縛り付けられる。
「わしは恐ろしいんじゃよ。許せ」
この場所に居続ける理由。
王であることの拒絶がそこにあった。
精霊ルビスとは…。
「どこかで聞いたことあるぞ」
それがどこであったか思い出せないのでサマル達に聞こうと思う。
武器屋を後にし歩き出す。
その後、丁寧に城の兵士に報告しておいた。どうにかしてくれるだろう。
ローレにはどうすることもできない。
「ローレ、お帰り」
宿屋に戻ったローレを迎え入れたのはサマルと目が覚めたムーンだった。
あの時の壊れた感じではないが虚ろな瞳が不安を覚える。
「ムーン起きたのか?」
「うん。少し落ち着いたみたい」
サマルがそう答えるも、返事のないムーン。
側に行き覗き込むもローレを見ているようで見ていない。
「ムーン! おれ達は生きてるんだぞ!」
ローレはムーンの両肩に手を置き、ムーンの視線を向けさせる。
サマルが少し驚いて止めようとしているが御構い無しだ。
「ルビスの加護がおれ達を守ってくれてる! だからどんな事があっても三人一緒だぞ!」
ローレが今言える最大の言葉である。
先程聞いた知識そのままにぶつける。
目をまん丸にしたムーンの瞳に光が戻った気がしたが、その後その目に涙を溜めて号泣した。
どの言葉がきっかけで感情が爆発したのか、何度もローレの肩や胸を叩き、服を握りしめ叫ぶ。
その叫びは何かを言っていたようだが、言葉として理解できない。
何が何だかわからないまま、支えるように抱きとめる。
そのまま泣き疲れたように眠った。
「サマル…」
どうしたもんかとサマルの方を見るといつもの穏やかな笑みを蓄えていた。
「ムーンは多分もう大丈夫だと思うよ。ちゃんと泣けたから」
涙は人の心の不安定さを和らげてくれる。
そして、衝撃により奥に潜めてしまっていた感情があふれて爆発した。
それは心が壊れるの堰き止めてくれる。
「三人一緒だと怖くないっか、無責任だけど力強い」
サマルは思う。
あの言葉は決してムーンが欲しかった言葉ではないだろう。
特別な存在になんてなりたくなかった。
何もわかってないくせに、どんなに辛いか理解できていないくせに、それでも責めることを許してくれる。
感情をぶつけることを許してくれる。
汚い感情を軽蔑しない、そんなローレに救われた。
確かにその通りだと頷く。
「そう言えば、ルビスの加護って何だ?」
その言葉に本当に何もわかってないことに、一瞬呆けてしまった。
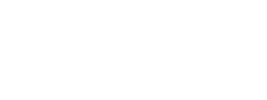
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます