「………」
熱で魘されている彼の顔を拭いてやる。
まさか、倒れてしまうなんて思わなかった。
ベロニカとセーニャは高い山育ちだったし、麓に降りるにはこの過酷な雪原をよく利用してしたので慣れっこであった。
暖かい地域の城育ちであるマルティナが『結構肌に突き刺さる寒さで体を動かしていないと直ぐに凍えそう』と、言っていたから、暖かいところに住んでいた彼も同じかも知れない。
「何があったのよ」
魔女が彼を半分以上凍らせていたところは見た。
慌てて魔法をぶつけたから良かったものの。
氷漬けにされるところだった。
あの吹雪の中、彼と逸れて慌てるも音がかき消されて、どこにいるか分からない状況だった。
彼以外と逸れなかったのは奇跡に近いかも知れない。
いや、もしかすると誰かが意図的に逸れさせたのかも知れない。
そんなことができるのは、城ごと城下町を氷漬けにしたあの魔女だけだが…。
動機は…。
憶測だけでは何も分からない。
恨みの気持ちが先行して思考がまとまらない。
一度、頭を横に振り、思考のリセットをかける。
彼は相変わらず懇々と眠っている。
「大丈夫って聞いたときは、頷いてたくせに」
自身が勝手にそう思ってしまったのかも知れないけれど、倒れるまで寒さを訴えることがなかったことには責めたい思いである。
「そう言う状況じゃなかったかも知れないけど」
確かに色んなことが一気に起きた。
ベロニカの中でもまだ整理し切れていないのは確かだ。
でも、そうじゃない。
そんなことを言いたいんじゃない。
気付けなかったことが悔しかったのだ。
だって、双子の姉妹が彼のそばにいる理由は、終始彼を護り安全に導くためだ。
「あたしは治してやれないのよ!」
同じ世界樹の葉から二つの生命が生まれたことで、能力が二分化された。
妹のセーニャは回復魔力に、姉のベロニカは攻撃魔力に特化した性能を持つ。
だから、敵にダメージを与え蹴散らすことはできても、傷付いた体を癒すことはできない。
「はぁー。ヤになっちゃう」
ちゃんとセーニャが傷と熱の治療をしているのに自分ができることがないかと思ってしまう。
今ほど子どもの体であることが恨めしいと思ったことはない。
悔いるなんて自分らしくない。何故こんなにも焦るのだろう。
皆はこの小屋を貸してくれた人と今後についての話し合い、確認作業と策を練るために一度外の様子を伺いに行っている。
何故か行く気が起きなくて、彼を見ていると言った。
皆に驚かれた、特におっとりしているのであまり驚くことのないセーニャが、目をまん丸にしていたのが印象的だった。
何でかな。
目が離せないのよね。
色んな加護に護られているはずの勇者。
でもそれはとても危ういものなのかもしれない。
誰かが、皆が護らなければ直ぐに朽ちてしまうようなそんな儚さが何処かにある。
「どんな事があっても光は滅ぼさせはしないわ」
賢者の生まれ変わりが二人である意味。
良いわよ。受けて立とうじゃない。
彼は儚い、でも何にも負けない勇気と光がある。
諦めの悪さも天下一品だ。
「だから、最後まで付きまとってあげるんだから、覚悟しなさいよ」
小さい手ではやはり摘みにくいと思いながら彼の鼻を摘む。
眉を潜めるも先程の苦悶の表情は和らいだ。
もう大丈夫だろう。
ベロニカは一人、誰にも見せないであろう優しい笑みを浮かべた。
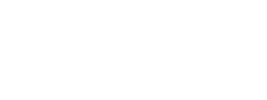
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます